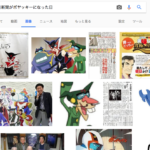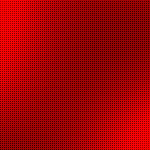新聞週間だそうです。そこでマイナビのタイトルですでに指摘しましたが、今回のお題はこれ。
「新聞は死んだ」
新聞の言論機関としての機能の衰退は永らく叫ばれていました。
わたしがものごころついた昭和50年代から言われていることで、当時の介錯人は「テレビ」でした。電波メディアとしては「ラジオ」もありましたが、ビジュアルというアドバンテージで、メディアの王者に君臨していた新聞は、テレビの登場、普及により「速報性」と「動画」の力に敗北しているという主張でした。
しかし、投げたボールが放物線を描き下落するように衰退しながらも、盟主に君臨し続けることができたのは、新聞が積み重ね研鑽してきた社会にとっての「知性」としての役割です。
速報性とビジュアライズでは「写真週刊誌」が時代を席巻したこともありましたが、下品と過激に走り「知性」としての品位を身につけることができず、テレビも右に同じです。
テレビもまた「画になる」ことにこだわるあまり、ニュースが偏ることも甚だしく、詳細報道において新聞の存在意義がありました。テレビ優位が叫ばれる中、テレビ朝日で『やじうま新聞』がはじまった(当初は番組内の1コーナー、ただし“やじうま”の冠はこの9月に消滅しました)のは象徴的な出来事です。
その新聞が死にかけています。
ネットがそこに取って代わるというものではない・・・と思っていましたが、やっぱり入れ替わるかも知れません。
マイナビの原稿でも触れたように、産経新聞の購読を先月末でやめました。理由のひとつは言葉の乱れです。
「モテ期」「ジモト」
一面コラム「産経抄」で登場します。産経抄といえば、かつては石井英夫氏が執筆し、足元に及ばないとは分かっていながらも、近づきたいと憧れのコラムでした。
新しい言葉を使うことが悪いというのではありません。しかし、新聞は老若男女の大半に情報を伝えるという使命があり、例えば
「モテ期(異性の好意が集中する時期があるという都市伝説)」
と説明を加えるものです。また、これこそ腕の見せ所で、
「モテ期(異性の行為が集中する時期があるという都市伝説。失礼、異性同性を問わずです)」
などと時代性をさりげなく織りこみます。というより、
「人生には恋愛感情を寄せる人が集中的に現れる時期があるという都市伝説を“モテ期”と呼ぶそうだ」
のように、括弧を使わない方が正当でしょう。ところが産経新聞では一切の説明無く用います。産経新聞のレベル低下を知人の編集者にメールをすると
「ドヤ顔」「ツンデレ」「ポチャモテ」
と、追加情報が返信されます。これがスポーツ新聞なら文句言いません。東スポならスルーです。しかし、保守を標榜する産経新聞が言葉の乱れを率先します。
産経新聞は民主党による政権交代後
「民主党さんの思うとおりにはさせないぜ」
とツイートした新聞で、これについては軽率な発言だったと謝罪しましたが、社の方針はそうで、ついでにいえば
「石原慎太郎の悪口は言わない」
が社是であることは、元記者の久保紘之(くぼ こうし)氏が『月刊Will』で語っています。極右雑誌と呼ばれる同誌らしいと思うのは、日本的な保守の価値観からすれば、同士であっても間違いは間違いと指摘するもので、身びいき、内輪誉めを恥ずかしい行いと律します。
話を戻せば、民主党政権時代、舌鋒するどく切り込んでいた誌面が、昨年12月の政権再交替以後、
「燃え尽き症候群」
であるかのように、すべての誌面が停滞しています。いま、読むに値するのは適菜収氏の不定期掲載「賢者に学ぶ」ぐらいです。ファンとしては曽野綾子ちゃん(失礼は承知の上ですが、文章から滲みでるお転婆なキュートさへの敬意です)。
また、ウェブにおもねることも多く、社会的に問題がある人物ともシェイクハンドします。オフレコで聞いたことで、ここで名前は挙げられませんが、マイナビの原稿で指摘した上杉隆氏だけではありません。
保守の防波堤としての産経新聞はすでに決壊し臨死状態です。
その他の新聞も似たり寄ったり。日経新聞については、この場で何度も指摘しているので、いまさらな感もありますが、株式の予想紙という性格からみれば「競馬エイト」と同じです。問題はこれを一流の情報紙と捉える錯覚にあります。元キャバ嬢と噂される、うつろいやすい音程のタレントくずれを「歌姫」と呼ぶような錯誤です。
朝日新聞は・・・まぁ言わずもがな。どんな誤報を出しても反省しません。イデオロギーに支配されているという点では日本共産党の機関誌「赤旗」と同じで、特定の編集方針により発刊されているという視点で見れば「聖教新聞」と同じです。
それでは世界最大の発行部数を誇る「読売新聞」はといえば、こちらは読売巨人軍偏向報道は・・・まぁ、見逃すとしても、いよいよもって死期が近いと分かったのは、本稿では何度も取り上げている古市憲寿氏を「社会学者」と紹介している点です。
新聞週間の特集記事で、山岸舞彩氏と対の見開きに、インタビューが掲載されます。古市憲寿氏の薄っぺらい発言は彼の持ち味というか、それしか引き出しがなく、本稿で取り上げるまでもないのですが、彼のプロフィールを読売新聞ではこう紹介しています。
“1985年生まれ。東大大学院博士課程に在籍中”
つまり、古市憲寿氏はまだ学生。過去にも読売新聞は「空想書店」という書評コーナーの企画で、古市憲寿氏を登場させ、実際の旅よりネットで検索という珍説を開陳したものを、そのまま掲載します。
古市憲寿の薄さは、その場限りをやり過ごしつつ、ぼくって人と少し違う視点を持っているんだぜ、へへへ。的なナルシストさから来るものです。社会学者を名乗る(新聞や雑誌に掲載される際、肩書きは必ず確認されるので、古市憲寿は学者と自称しているということです)のであれば、自己の発言を学樹的な視点から解析して欲しいと切に願いますが、その能力があればもっとまともな発言をしていることでしょう。
先の「旅よりもネットで検索」は、わたしの意訳ですが、ようするに書評コーナーで気に入られるたびに、旅よりも本と言いたかったのでしょうが、書評家の誰もがこれに異論を唱えることでしょう。なぜなら
「本は別世界を体験させてくれるが、実体験を越えるものではない」
からです。創作が現実に優るなら、『美味しんぼ』を読んで空腹を満たせば良いのです。ただし古市憲寿氏に『ミスター味っ子』を読ませるのは危険です。フィクションと現実を混同し、またいらぬ妄言を量産することになるからです。
身体が不自由で旅に出られないという前提条件での話しではありません。仮にそうであっても、横たわったベッドから見上げた秋の空に浮かぶ、リアルな鰯雲に感動するこころを持つのが人間です。
読書と旅は、むしろ優劣をつけるものではないでしょう。旅で触れあう人々の接触に難色を示し、実際の風景よりプロのカメラマンが撮影した写真を古市憲寿は礼賛します。あまつさえ、持論のために、モンサンミッシェルを「観光地」と切り捨てるに当たっては、読売新聞に見識があれば「ボツ」にすべき主張です。
そしてこの時も彼を「社会学者」と紹介します。
ただの記事なら古市憲寿がまた調子に乗っているなぁとつぶやく程度ですが、新聞週間の企画です。しかも、です。消費税増税にあたり
「新聞に軽減税率の適用を」
として、天下の公器(新聞のことらしい)を盾に主張するのであれば、見合った見識を示さなければなりません。
そこで読売新聞の読者センターに電話を掛け
「なぜ、学生を社会学者と称するのか」
と問いかけます。電話を受けた担当者は「たしかに」と言葉を詰まらせ、社内で調べ、折り返し電話することを約束します。
1時間ほど経った頃、返信があります。あらかじめ触れておきますが、言葉遣いも応対の物腰も丁寧でした。
そしてその回答はこんな感じ。
「フィールドワークなどもされており、著作を発表されていることなどを総合的に判断して社会学者とした。学生だということで学者でないという判断はしない(要約)」
突っ込みをいれます。フィールドワークを怠らず、著作を執筆しているものは「研究者」ではないか。あるいは「作家」も同様だ。飛躍をすればカフェでの人間観察から作詞をする「松任谷由実」ですら学者になってしまう。学者という表記を裏打ちするアカデミックな担保はないのか等と、いくつかのツッコミに対して、ときおり絶句するも、読売新聞社としてはそのように考えていないと回答。
論戦・・・いや、口喧嘩ならわたしの圧勝です。しかし、電話の向こうの担当者は、言葉を濁しながらも「しかし」と区切ってから「総合的に勘案した結果、そのように判断している」と繰り返します。
ピンと来て、こう切り出します。
「わたしが知りたいのは読売新聞社としての見解。古市憲寿のような学生でも“学者”と紹介するのが貴紙の見解ならば、それを訂正させようなどとは思っていない」
電話の向こうから安堵が伝わってくるようです。読者センターには折伏を迫る○○学会からの電話が多いのかも知れません。そして念を押します。
「つまり読売新聞にはアカデミックな裏付けがない独自に判断した情報が掲載されるということですね」
これには、そうだとしか答えようがないでしょう。アカデミックな裏打ちなしに古市憲寿氏を「学者」とするのですから。
それではと「ウィキペディア」で「社会学者」をひいてみます。
「古市憲寿」という名前は本日現在見かけません。
この時点で、「社会学者」においては、わたしは新聞を信用せずウィキペディアにあたります。
わたしのなかで読売新聞が死んだ瞬間です。
読売新聞への電話取材と、ウィキペディアとの比較で、新聞の死亡理由が少し見えてきました。
「自己検証能力=反省」
です。
朝日新聞に顕著ですが、読売新聞の読者センターの担当者も、決して自説を曲げようとしません。ヤンキー用語における
「吐いた唾は飲むな」
です。自説に固執するということは、成長しないことと同義です。無知の知をあげるまでもなく、森羅万象の全てを知るものなど、地上に一人もいはしません。もちろん、間違いだってあります。ところが新聞社だけが、その記者達はみずからの過ちを認めず、主張を撤回しないのです。
個人個人では柔軟な記者もいます。ところがそれが新聞になったときに、社論のまえに思考停止します。
産経新聞の「産経抄」は社内においてひとつの権威です。しかし、新語や流行語、一時のブームによる言葉を軽々に使うその姿勢は、ネットにおもねる卑屈さの発露です。そしてそれを社内の誰も批判しないのですから、やはり、新聞は死んでいます。